
第2回WRHI講演会が行われました
イベント報告
第2回WRHI講演会開催報告 (2017年7月12日)
7月12日午後に、R2棟1階オープンコミュニケーションスペースで、第2回WRHI講演会が開催されました。前回と比べると参加者が増え、本講演会が定着しつつあるようです。今回も、フロンティア材料研究所の東正樹教授の司会で、WRHIプログラムによって海外より招聘した3人の研究者が自らの研究について講演しました。
 会場の様子
会場の様子  司会の東教授
司会の東教授 
最初の講演者は、豪州のMonash Universityより招聘され、大隅研究室所属のDr. Alexander I Mayです。 “The physiological role of autophagy in metabolically transitioning cells” と題して講演しました。これは、細胞が代謝する際のオートファジーの役割について述べたものです。
先ず出芽酵母の説明から始まりました。出芽酵母は糖を代謝してアルコール発酵することが古来より知られています。この代謝の際に、オートファジーがどのような役割を果たしているのでしょうか。オートファジーは細胞の中の構成物を自ら食べる(分解する)生物のリサイクルシステムです。オートファジーの欠損株を利用し、野生型に比べて成長に欠陥があることが観測されました。ところが、ある種のアミノ酸を補充することによってオートファジー欠損株における生育不良を救済できることが確かめられました。また、この代謝系の中では細胞中のミトコンドリアにタンパク質を合成する過程に必要となる核酸修飾がオートファジーによって進行し、これが代謝やタンパク質変換を促進することが分かりました。本講演はオートファジーに関する最新の話題を提供してくれましたが、この分野は新しく、しかも複雑なプロセスも含んでいます。これからも未知の世界の解明が待たれます。
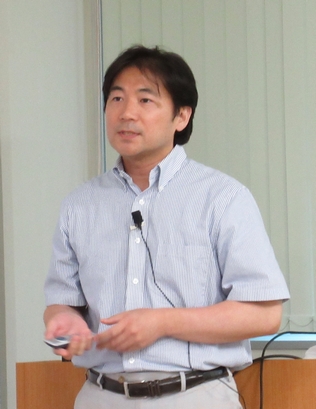
次に Dr. Kenji Suzuki が “Artificial Intelligence in Medical Imaging”と題して講演しました。Dr. Suzukiは計算知能と医用画像解析の研究をシカゴ大学で13年,その後イリノイ工科大学で3年しています。
最初に、コンピュータ支援診断とは何かを,日本でもお馴染みの「ウォーリーを探せ!」を用いて、分かり易く説明しました。コンピュータ支援診断では、人工知能(Artificial Intelligence: AI)が病巣の候補を自動的に検出し、これを医師が「第2の意見」として利用して最終的な診断をします。このAIの中心的な役割を果たす技術が機械学習です。様々な形態を持つ病巣や臓器を表現するためには、複雑なモデルが必要ですが、この複雑なモデルが持つ膨大なパラメータを、手作業で決めることは不可能です。これらを、「例からの学習」により合理的かつ自動的に決めるのが機械学習です。このため、AIによる診断支援にはこの技術が必要不可欠です。従来、このようなAIでは、医用画像から病巣を分割し、分割した病巣から特徴量を抽出し、それらを機械学習に入力し、これら特徴量に基づき病巣を識別していました。大人が対象物を特徴や言葉で説明することから、これを「大人のAI」と呼びます。しかし,このような従来の機械学習法では、多くの場合、医師の診断能に追いつくことができませんでした。Dr. Suzukiらは、1996年に画像を直接学習する機械学習を開発し、これを2003年にコンピュータ支援診断に応用しました。この新しい機械学習は、幼児や子供が見たものを直接学んでいくように学習することができます。これにより、AIの性能が飛躍的に向上しました。これを「幼児のAI」と呼びます。ごく最近になって、同種の手法がディープラーニングと呼ばれ,学会や産業界で大変な大きな話題となっています。今後、ディープラーニングを含むAIが診断支援システムの性能を飛躍的に向上させ、医療を大きく変えていくと予想されています。Dr. Suzukiが先駆的に開発した「幼児のAI」手法は、汎用性が極めて高く、様々な分野への応用と展開が期待されています。

最後の講演は、ミシガン大学の生命科学研究所より大隅研究室に招聘されたDr. Yui Jin による”Intracellular organelle dynamics during cell division cycle”です。
細胞の内部に存在する細胞小器官(organelle)は幾つかの構造体、例えばミトコンドリア、液胞、ゴルジ体、エンドソーム等から構成されています。今回のトピックスは、細胞分裂をする際に細胞小器官で、どのような現象が起きているかを解明することです。細胞分裂が始まると、親細胞から突起した子細胞が次第に大きくなっていきます。そして、細胞分裂後には子細胞は親細胞と同じ細胞小器官を持つことになります。これを可能とするのがミオシンと呼ばれるタンパク質で、分裂中の細胞の中で細胞小器官を運搬する役割を担います。この様にして細胞分裂は進みますが、中には液胞が輸送されなかった子細胞であっても液胞が合成され細胞分裂が可能であることも分かりました。この研究は現象を一つ一つ解明していく生命科学分野の地道な基礎研究ですが、今後どの様な形で社会に貢献できるか注目していきたいと思います。
活発な意見交換後、本講演会は無事終了しました。これと同時に、隣接するロビーで科学技術創成研究院の教職員や学生が参加した懇親会が始まりました。講演会の緊張感から解放され、参加者はビールを片手に夏の夕暮れを大いに楽しみました。



