
第1回WRHI講演会が行われました
イベント報告
第1回WRHI講演会開催報告 (2017年6月7日)
新たにR2棟1階にオープンしたオープンコミュニケーションスペースで、6月7日に第1回WRHI講演会が開催されました。これは、WRHIプログラムによって海外より招聘したトップレベルの研究者が自らの研究について語り、会場の聴衆とディスカッションをするものです。今回は30人余りの方々が参加され、会場はほぼ満席でした。 講演会は座長の東正樹教授の司会で進められ、3名の講演者が発表しました。
 会場の様子
会場の様子  東教授
東教授 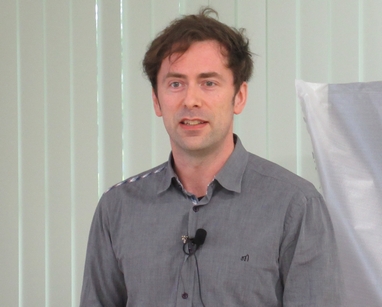 Dr.Petter Holme
Dr.Petter Holme 最初の講演は、Dr.Petter Holme による”Temporal networks of human interaction”です。このテンポラル・ネットワークとは、2つのノードのつながりに時間の概念も加えたものです。特に感染症の広がりの説明には適しており、近年時間情報を含むネットワーク・データが利用可能になっている背景を受け、そのデータ解析理論を確立する研究に注力し、最新のネットワーク理論の位置づけを示しました。Dr.Holmeの研究は、旧来の静的なネットワーク手法では解けない、ダイナミックな挙動、事象への応用が期待されます。
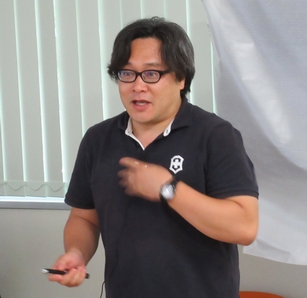 Dr.Norimasa Nishiyama
Dr.Norimasa Nishiyama 続いて、Dr. Norimasa Nishiyama が “Very tough hardest oxide and transparent third hardest material”について講演しました。 ここで扱った材料は2つあり、ともに一般的な二酸化ケイ素(SiO2)と窒化ケイ素(Si3N4)です。これらに高い圧力を加え、その性質がどのように変化するかを研究しました。SiO2では、地下マントル層のSiO2構造であるstashoviteと呼ばれるものと同等な硬い特性を実現できました。また、Si3N4はスピネル構造に変化し、ダイヤモンド、立方晶窒化ホウ素(cBN)に次ぐ3番目の硬さを実現し、また高い透明性も得られました。このような高圧による物質の特性変換手法が、新しい有用な材料の開発に寄与するものと思われます。
 Dr.Chandra Debraj
Dr.Chandra Debraj 最後の講演は、Dr. Chandra Debraj による “Smart architectures of nanomaterials as heterogeneous catalytic system for versatile applications”です。最近の触媒研究でのトピックスを紹介していただきました。これまでにナノ材料分野ではいくつかのユニークな構造が開発され、異種物質の触媒作用や太陽光による水分解等の様な用途に適用されています。また、バイオマスへの変換分野では、金属触媒のフラットRuナノ粒子がフランアルデヒドを還元的にアミノ化し、付加価値の高い化学物質を創りだすために優れた触媒作用を示すことが分かりました。更に酸化タングステン(WO3)を光触媒として小さなメソポア系においても初めての高温結晶化が達成され、この技術は他の未結晶の結晶性材料化の可能性を示すものとして注目されています。触媒については、これからも多くの分野で様々な応用が期待されています。
WRHI講演会は今回が初めてですが、学内でのオープンコミュニケーションスペースでの短時間でリラックスした雰囲気の中で、最先端の研究成果が披露されました。次回は同じ場所で7月12日です。是非、ご参加ください。
