
開催報告:第4回WRHI講演会(12月12日
おすすめ イベント報告
第4回WRHI講演会開催報告 (2018年12月12日)
今回で第4回となるWRHI講演会が、12月12日にR2棟1階のオープンコミュニケーションスペースで開催されました。本講演会は、世界の第一線で活躍しているWRHI招聘研究者が、最新のトピックスを提供し、議論する場となっています。今回のテーマは材料分野から2件、脳科学分野から1件の講演がありました。司会は、前半を大竹尚登科学技術創成研究院副研究院長が、後半をフロンティア材料研究所(WRHI運営委員会委員長)の東正樹教授が務めました。



最初の講演者は、インド工科大学Madras校のバイオテクノロジー部門の教授であり、本学のスマート創薬研究ユニットの特任教授として招聘されているDr. Michael Gromihaで、講演テーマは”Integration computational methods and experimental data for understanding the binding affinity of protein-protein complexes”です。
細胞内のあらゆる生物学的システムは、タンパク質により制御されます。タンパク質の研究は、その構造、動的なたたみ込み、安定性や相互作用等のために、科学的解明が難しいけれど大変やりがいのある分野になっています。この課題に対し、ある立体構造のタンパク質-タンパク質複合体における原子間距離や溶媒露出面積を調べて界面における結合部位を特定し、その相互作用エネルギーをコンピューターシミュレーションで求める分析方法を開発しました。そして、タンパク質 – タンパク質の結合親和性に関するデータベースを作成してタンパク質間複合体の特性を予測するための計算方式を確立しました。
このようにコンピュータを利用して多くの可能性を参照する方法は、様々な可能性の中から特定のタンパク質や小分子を選ぶ方法であり、それはタンパク質の構造と機能の科学的メカニズムを探究するだけでなく、創薬のタイムリーな開発にも効果的であると期待されています。
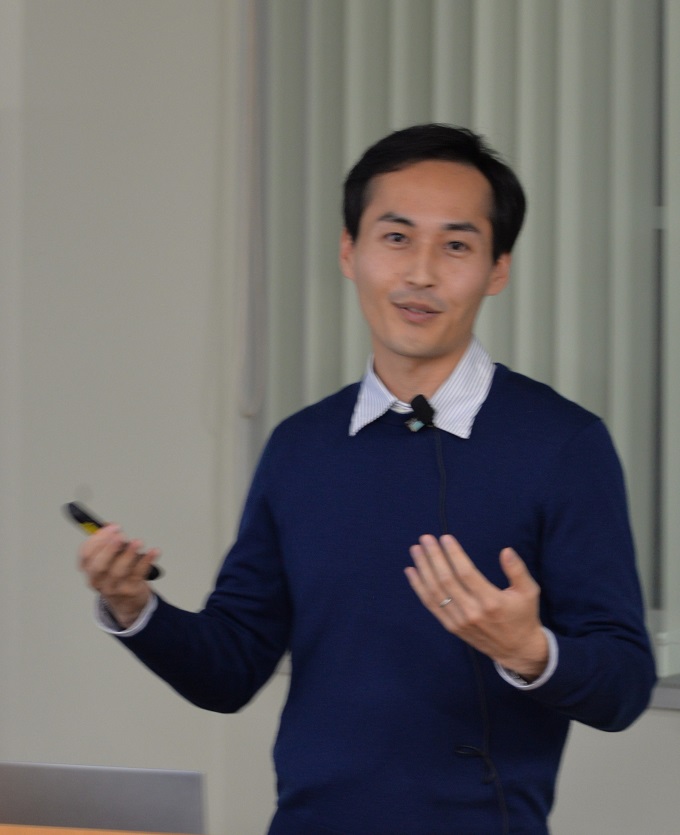
次の講演は、Dr. Atsushi Takagiによる”How humans move, interact, and adapt to their environment”です。先生は英国インペリアルカレッジロンドンから、2017年に本学バイオインターフェース研究ユニットの特任助教として赴任しました。専門分野は計算論的神経科学で、研究対象は人と人との相互作用です。
2人で荷物を運搬したり、ダンスをしたりするとき、人はどのように身体の動きを調整するのでしょうか。人と人との情報交換の手段には様々な方法がありますが、ここでは物理的な力、特に触覚に着目します。ペアの被験者がおり、それぞれがロボットインターフェースのハンドルを握ります。個々の被験者は、自分のモニタにカーソルとして表示されている自分の手を動かすことによって、動いているターゲットを追跡します。 ここで2人の被験者の手は、仮想的に輪ゴムでつながっているとします。各被験者は、パートナーの動きから生じる手の触覚力を感知し、被験者が単独で練習しているときよりも早く追跡のタスクを習得することができます。このような触覚的な協調性は、被験者数を3人と4人に増やすことで更に改善されることが確認されました。また、2人の被験者のうちの1人をロボットパートナーとしても同様の結果が得られました。この結果、被験者は触覚を通して相手の目標を推論し、ターゲットを追跡するときの視覚と触覚による統合的な感覚が被験者に身体的な相互作用を及ぼし、彼らのタスクパフォーマンスを改善することが出来ました。
この研究は、人間のパートナーの意図を推定する協調ロボットの開発に役立つばかりでなく、ロボット理学療法士を創り出して多数の脳卒中の患者を助けることも出来るようになるかもしれません。

本日最後の講演は、米国のCornell大学よりフロンティア材料研究所に特任准教授として赴任されたDr. Hena Dasによる”Material Specific Theoretical Approach to Understand and Predict Quantum phenomena in Materials”です。
先生のご専門は、理論材料物理学であり、その目的は多様な科学的及び商業的用途につながる新しい高性能材料を創り出すことです。先生は、強磁性、強誘電性、磁気電気効果、スピン軌道、負の熱膨張等、様々な特性を示す材料のマクロ的な性質の根源を調べています。
このような量子現象を理解し予測することは、1998年にノーベル化学賞を受賞したWalter Kohn博士によって開発された手法である密度汎関数理論(Density Functional Theory)を応用して構築されたハミルトン関数を使用することで可能となります。このようにして、ある温度範囲で相の安定性やマクロ的な現象を分析することができるようになりました。そこで講演では、最近の研究成果として、電池の充放電プロセス中の酸素損失の結果としてのNiベースのLiイオン酸化物電極材料の構造相の安定性について解析し、電池の性能に対する酸素欠乏相の形成の影響、及びその改善の方向性について詳細に説明しました。
このように、理論体系に基づき物質のミクロ的な世界を調べ、候補物質の合成、検証を進める手法は、斬新で汎用的なものであり、新たな材料の開発が期待されます。

講演会が終わるころには、師走の陽はすっかり沈んでいましたが、講演者を中心に議論の輪が続いていました。
